2020年10月に読んでよかった本をまとめます。
『哲学と宗教全史』出口 治明 (著)
「ビジネス書大賞2020 特別賞受賞作」になった本書は、出口さんの本で哲学+宗教だから絶対に面白いに違いないと思っていました。
しかし、しばらく前に購入していたもののなかなか読めず、ようやく読み終えました。
基本情報
- 発売日:2019/8/8
- 著者 :出口 治明 氏
還暦で世界初のインターネット生保(ライフネット生命)を立ち上げ、古希で日本初の学長国際公募により立命館アジア太平洋大学学長に就任した稀代の読書家 - 池谷裕二氏、宮部みゆき氏、なかにし礼氏、入山章栄氏など各界論客から大絶賛!
- 「読者が選ぶビジネス書グランプリ2020」総合グランプリ第6位・リベラルアーツ部門第2位!
- 台湾、韓国からも翻訳オファー!
- 古代ギリシャから現代まで100点以上の哲学者・宗教家の肖像を用いて日本人最大の弱点、「哲学と宗教」の全史を体系的に語る
ハードカバーで超分厚い本です。
内容も古代ギリシャから現代までの広大な範囲をカバーし、内容も哲学+宗教ということで難解な印象があります。
しかし、記載されている内容はかなり平易で、初心者でも十分理解できる内容。
西洋中心の「哲学+宗教」だけではない
古代ギリシャからカント、ヘーゲルなどヨーロッパを中心とした哲学とか宗教をまとめている本はよく見る印象です。
個人的にこの本を読む意義は、西洋だけではなく、中国や中東、インドなどの哲学・宗教も並列で記載されていることだと思います。
出口さんの記述を見ても、「ヨーロッパでこういう考え方が生まれたが、実はその前には・・・」という形がいくつか見られました。
哲学や宗教と聞くとどうしても「ヨーロッパのもの」という印象を抱きますが、そうではないことが丁寧に書かれています。
むしろ東洋の哲学などを西洋が輸入している部分も多々あることがわかります。
学校の教科書とはまた違う視点で、世界を見ることができます。
各章の終わりに、オススメの文献も記載されているのが嬉しいですね。
この本は超入門編であるため、興味を持った分野をさらに学んでいきたいと思う意欲を沸かせてくれる一冊でした。
『人新世の「資本論」』斎藤 幸平 (著)
タイトルとカバーにまず惹かれました。
現在けっこう話題になっている一冊ですね。
個人的には、プチ・マルクスブームです。
(現代の社会の一部の流れとして、明らかにそういう傾向があると感じますし。)
基本情報
- 発売日:2020/9/17
- 著者 :斎藤 幸平 氏
1987年生まれ。大阪市立大学大学院経済学研究科准教授。ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士(哲学)。専門は経済思想、社会思想。
権威ある「ドイッチャー記念賞」を歴代最年少で受賞 - 人類の経済活動が地球を破壊する「人新世」=環境危機の時代。
気候変動を放置すれば、この社会は野蛮状態に陥るだろう。
それを阻止するためには資本主義の際限なき利潤追求を止めなければならないが、資本主義を捨てた文明に繁栄などありうるのか。
いや、危機の解決策はある。ヒントは、著者が発掘した晩期マルクスの思想の中に眠っていた。
世界的に注目を浴びる俊英が、豊かな未来社会への道筋を具体的に描きだす。
30歳ちょっとの若手研究家による意欲作。
「SDGsは大衆のアヘンである!」という印象的な書き出しから始まります。
資本主義による外部化によって、地球環境は崩壊寸前になっている。=人新世(環境危機)の時代」
それを乗り越える手段として、資本論以降のマルクスを読み解くことによって考えられたのが、「脱成長コミュニズム」。
これまでのマルクス論とは違う新たなマルクス像が読み解けます。
晩年のマルクスが唱えた「脱成長コミュニズム」
個人的には、環境問題に関して、非常に危機感を感じています。
特に、1次産業が身近な地方民としては、環境変化は地域の存続を揺るがしかねません。
一刻も早い取り組みを政治、コミュニティ、企業、個人が実践しなければ、我々が住む世界は変わるということを認識すべきだと思います。
しかし、経済活動の発展を目指す社会と相反する方針のため、なかなか進まないのが現状です。
SDGsが近年はどこでも聞かれるようになりましたが、単なる設定値であって、ビジョンなき目標になっている印象。
さらに、山形県内を見れば、SDGsすら知らない企業が、全体の3分の1というレベルの低さ(帝国データバンクの調査による)。
そんな状況を変える小さな光を、本書は見出してくれました。
これまであまり明らかにされてこなかった晩年のマルクス資料から、「脱成長コミュニズム」を提唱します。
知識、自然破壊、人権、社会といった資本主義による外部転嫁で破壊されたコモンを意図的に再建することを掲げます。
脱成長コミュニズムの具体的方針としては、次の5つ。
- 使用価値経済への転換
- 労働時間の短縮
- 画一的な分業の廃止
- 生産過程の民主化
- エッセンシャルワークの重視
「世界の3.5%が変われば世界は変わる」と最後に述べており、個人の小さな行動が大事であることを強調して本書は終わります。
非常に共感できる内容でした。
実際にこれがどう社会に影響するかはまだまだの部分があるのでしょうが、筆者によるさらなる思想の体系化・精緻化が楽しみです。
『ハイパーハードボイルドグルメリポート』上出 遼平 (著)
流行ってるので買って読んでみたら、予想以上に面白かったです。
その後、ネットフリックスで番組も見ましたが、本のほうが細かく状況や背景を描写しているため断然本派です。
基本情報
- 発売日:2020/3/19
- 筆者 :上出 遼平 氏
テレビディレクター・プロデューサー。1989年東京生まれ。早稲田大学を卒業後、2011年株式会社テレビ東京に入社 - 「ヤバい世界のヤバい奴らは何食ってんだ!?」「食の現場にすべてが凝縮されている」
テレ東深夜の単発番組としてスタートしながら、“他じゃ絶対にありえない”その内容で視聴者に衝撃を生んだ人気番組が書籍化。
人食い少年兵・マフィア・カルト教団……。
何が正義で何が悪か、“ヤバい”と“ふつう”の境界線とは―――。
数多の危険と困難を乗り越えた先の取材で、「食」を通じて描かれる世界のリアルとは
もともとは、テレ東の人気番組のようです。
(映らない地域なので知りませんでした)
ヤバい場所のヤバい人たちに密着取材で明らかになること
自分が体験できないことを知ることができるのが、本の魅力の1つだと思います。
ヤクザとか売春婦とかの物語とかもけっこう好きでために読むので、この本もかなり好きな部類のジャンルでした。
まさに自分ではとても体験できないリアルが仮想体験できます。
元少年兵、汚染されたゴミのたまりに住む人など想像しようがない人々のリアルがあります。
その人にはその人なりの置かれた立場があるということ。
我々は批判したり、助言したりすることはできるけど、まずなぜそのような暮らしをしているのか、どんな思いで生活しているのかを理解することが必要なんですね。
筆者の取材姿勢としても、ありのままを伝えたいという想いが伝わってきました。
個人的には、グルメ番組自体に興味はなく、食事の内容はあまり面白いとは思えなかったかな。
あくまでも世界の中の見捨てられた人々にスポットを当てる物語としての面白さでした。
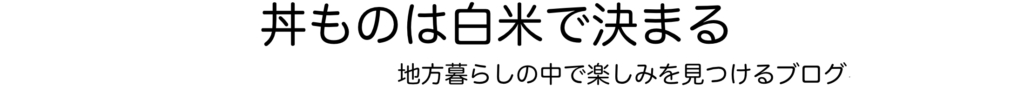
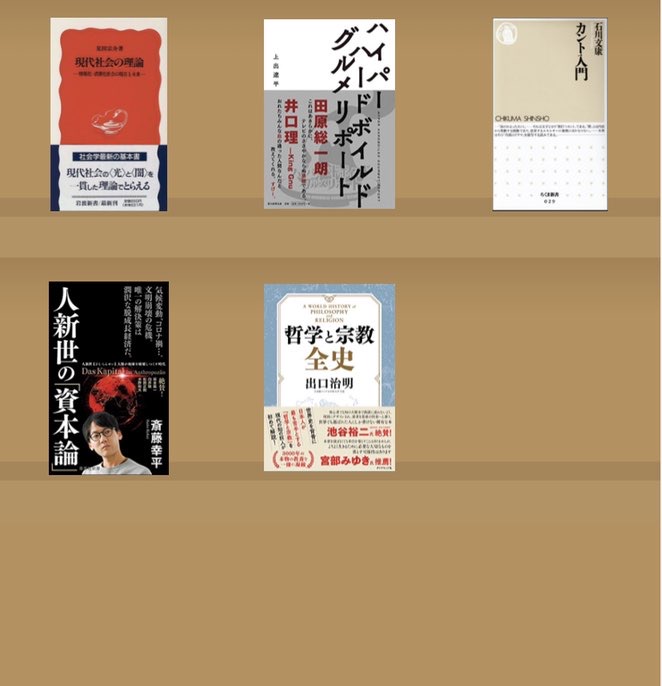





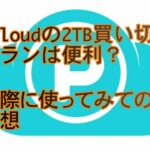
コメント